看護や介護の現場では、避けることのできない「別れの瞬間」。
そのたびに、心が揺れたり、言葉を失ったりした経験はありませんか?
グリーフケアとは、そんな場面で「どう寄り添うか」を考えるケアの形です。
「悲しみを癒す」のではなく、「悲しむ人と共に歩む」——。
この言葉の意味を理解することが、現場での支援の第一歩となります。
グリーフケアとは
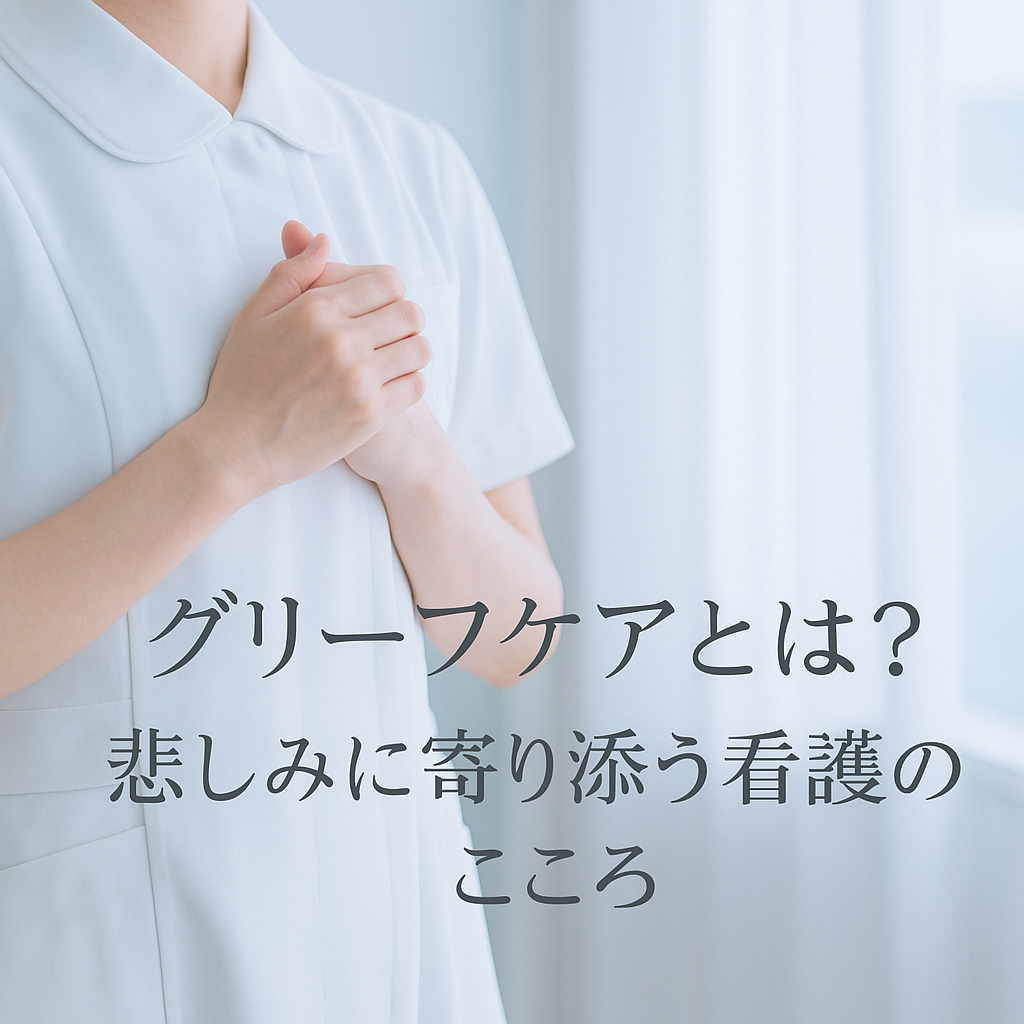
グリーフケアとは、「悲しみを癒す」のではなく、「悲しむ人と共に歩む」支援のことです。
人が大切な存在を失ったとき、心の中には喪失・後悔・罪悪感・孤独など、複雑な感情が渦巻きます。
それを無理に“元気づける”のではなく、その人のペースで悲しみを感じ、語り、整理していけるよう寄り添うのが、グリーフケアの基本です。
看護や介護の現場では、死別は日常の一部です。
しかし、そこには必ず“人の物語”があり、残された方の悲しみには一つとして同じものはありません。
「何かをしてあげる」のではなく、「一緒にいる」という姿勢が何よりも大切になります。
グリーフ(悲嘆)は時間と共に薄れるものではなく、形を変えながら人生に溶け込んでいきます。
そのプロセスを尊重し、焦らせず、安心して悲しみを表現できる場をつくることが支援の核心です。
医療従事者としての私たちは、忙しさの中でも「その人の悲しみに立ち止まる勇気」を持ちたいものです。
“癒す”のではなく、“共に歩む”。
それが、ケアの本質であり、人としての優しさそのものです。
看護師ができること
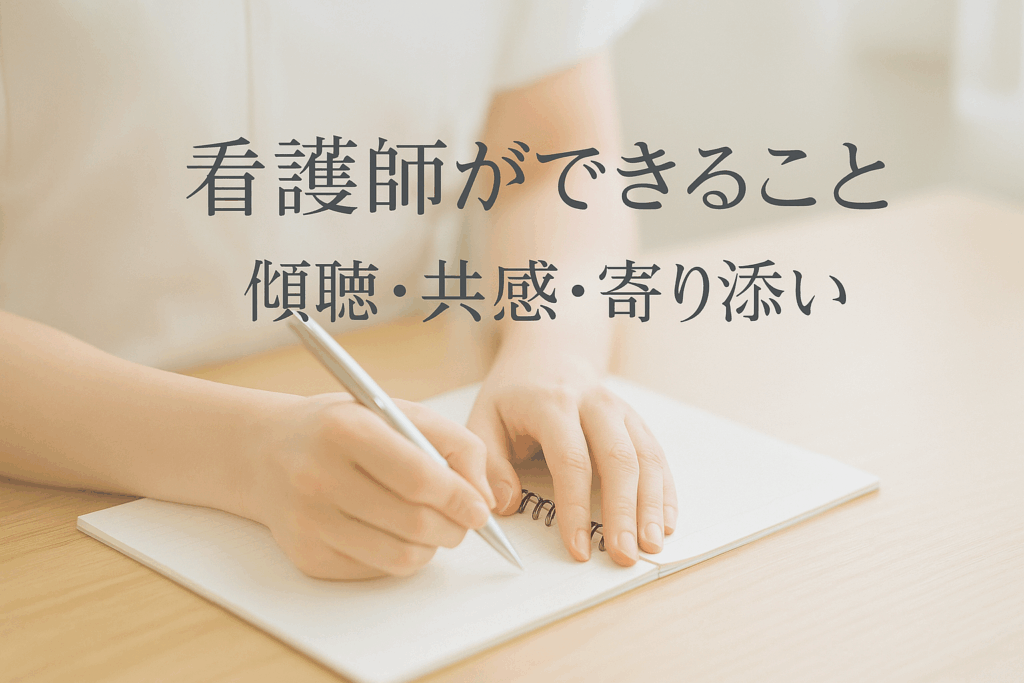
グリーフケアにおいて、看護師が果たせる役割はとても大きいものです。
患者の最期を看取り、遺族と最も近い距離で関わる立場にいるからこそ、
「寄り添いの姿勢」が周囲に安心を与えます。
看護師が行うグリーフケアとは、特別なテクニックではなく、
一人の人間として相手の痛みに寄り添うこと。
小さな言葉と態度が、悲しみの中の希望を灯します。
遺族支援の3ステップ
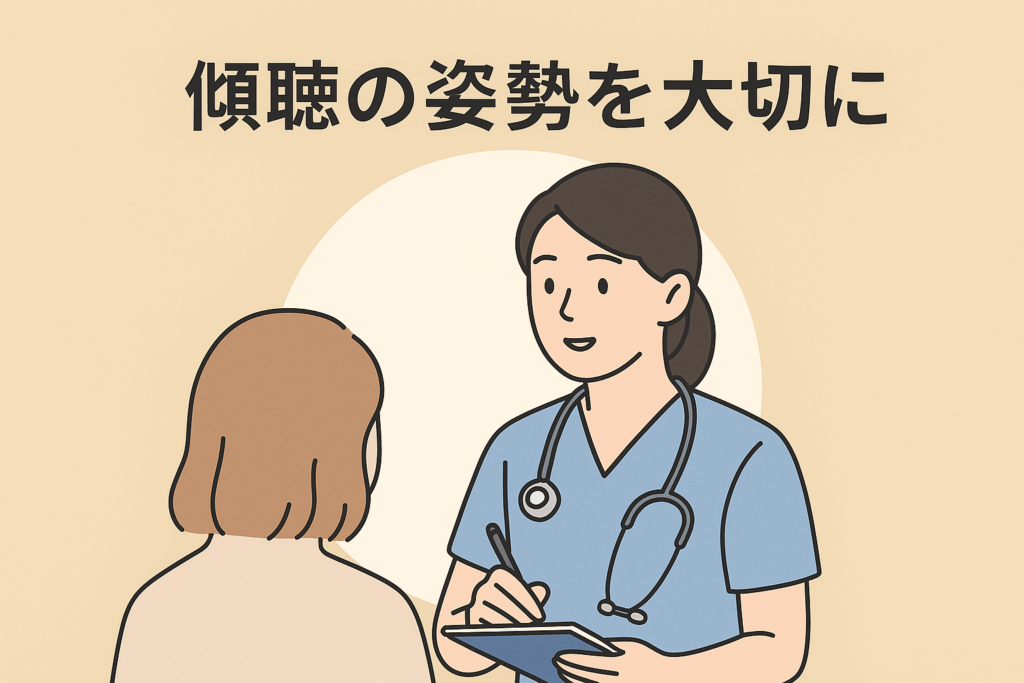
遺族支援を実践するうえで、看護・介護の現場で意識しておきたいのが「3つのステップ」です。
① 感情を受けとめる
まずは、相手の感情を否定せずに受け止めます。
「まだ信じられない」「何も感じない」「後悔ばかり」——
どの反応も自然であり、“正しい悲しみ方”など存在しません。
「そのように感じているのですね」と共感することから始めます。
② 安心をつくる
悲しみの中では、人は不安定になりやすいものです。
落ち着いた声、穏やかな表情、静かな環境づくり。
こうした“非言語的な支援”が、相手の心に安全基地をつくります。
「ここでは安心して話していい」と思えるだけで、心は少し軽くなるのです。
③ 社会的支援へつなげる
グリーフケアは一人の看護師だけでは完結しません。
心理士・医療ソーシャルワーカー・地域包括支援センターなど、
多職種で連携し、継続的に支援できる体制を整えることが重要です。
悲しみを一人で抱え込まないよう、社会的なサポートへ橋渡しをすること。
それも、看護師の大切な役割です。
この3ステップを意識するだけで、遺族支援の質は確実に高まります。
現場で迷わないために
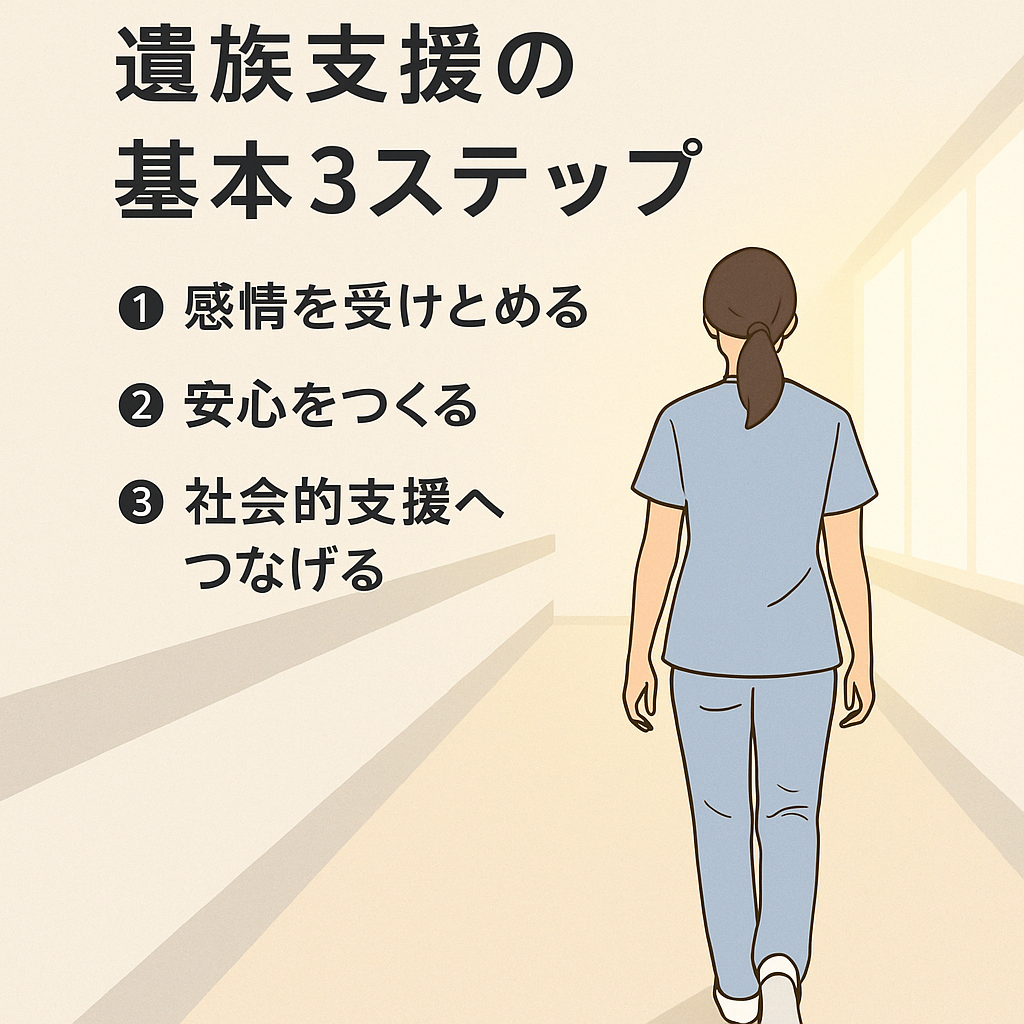
看護師や介護士が、死別の場面で「どう対応したらいいのかわからない」と感じるのは自然なことです。
正解のない場面に立ち会うからこそ、私たちは迷い、悩み、揺れます。
その迷いを少しでも軽くするためには、「自分なりの支援軸」を持つことが大切です。
それは「正しい対応」ではなく、「自分が大切にしたいケアの姿勢」です。
たとえば、「沈黙を尊重する」「相手の気持ちを否定しない」「形だけでなく心で寄り添う」など、
一つひとつの信念が迷いを減らす“羅針盤”になります。
また、現場で感じた葛藤は、同僚やチームで共有しましょう。
グリーフケアは、支援者自身の心のケアも欠かせません。
語ることで整理され、支援の質も深まります。
そしてもう一つ。
「悲しみを完全に癒すことはできない」という前提を受け入れることです。
だからこそ、“共に歩む姿勢”が尊いのです。
どんな場面でも、看護師の優しさと誠実さは、確実に相手に届いています。
あなたの存在そのものが、すでにグリーフケアなのです。
『グリーフケアと遺族支援ハンドブック』が支えになります
看護師・介護士の声から生まれたPDF教材
**『グリーフケアと遺族支援ハンドブック』**では、
現場で「何をどうすればいいか」がすぐにわかる内容を収録しています。
✔ 声かけ例文集
✔ 感情段階モデル図
✔ チェックリスト
✔ ケース別対応例
「癒す」ではなく「共に歩む」ために。
あなたのケアを支える、1冊のハンドブックです。
👉 詳しくはこちら
▶ ココナラで教材を見る
まとめ
「悲しみを完全に癒すことはできない」。
その事実を受け入れたとき、初めて本当のグリーフケアが始まります。
看護師の誠実なまなざし、やさしい沈黙、思いやりのある一言。
それらすべてが、誰かの心を支える“看護の力”です。
あなたの存在そのものが、ケアの証です。


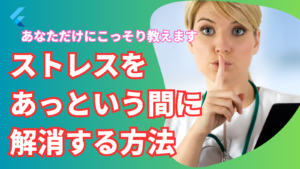


コメント